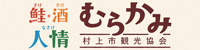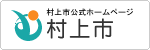本文
北前船日本遺産
記事ID:0033356 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示
令和6年6月、村上市を含む3自治体(村上市・福井県美浜町・岡山県岡山市)が、文化庁が認定する日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」に追加認定されました。これにより、北前船日本遺産の認定自治体は16道府県52自治体となり、新潟県内では新潟市・長岡市・佐渡市・上越市・出雲崎町に次ぐ認定となりました。
【問い合わせ先】
村上市教育委員会 生涯学習課 文化行政推進室 0254-53-7511
北前船と日本遺産
日本遺産とは
「日本遺産」は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを日本遺産として文化庁が認定するもので、ストーリーを語る上で欠かせない有形・無形の様々な文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより地域の活性化を図ることを目的としています。
北前船日本遺産のストーリー(概要)
日本海や瀬戸内海沿岸には、山を風景の一部に取り込む港町が点々とみられます。そこには、港に通じる小路が随所に走り、通りには広大な商家や豪壮な船主屋敷が建っています。また、社寺には奉納された船の絵馬や模型が残り、京など遠方に起源がある祭礼が行われ、節回しの似た民謡が唄われています。これらの港町は、荒波を越え、動く総合商社として巨万の富を生み、各地に繁栄をもたらした北前船の寄港地・船主集落で時を重ねて彩られた異空間として今も人々を惹きつけてやみません。
北前船と村上市
村上地域の海運業は江戸時代中期~明治時代中期に最も盛んとなり、明治時代後期以降に大型汽船の就航、鉄道による輸送が本格化するまで海運業が地域を支える重要な役割を果たしてきました。村上地域では新潟~酒田間約100キロメートルで積荷を運ぶ小型船の往来とともに、江戸時代後期以降は北海道から大阪の間を運行する北前船による回船業も盛んになり、山北・上海府・瀬波・岩船・塩谷・海老江には海運業関係者が多数存在しました。現在も各地に残る港町の町並みや社寺に奉納された船絵馬などから、その歴史がうかがえます。