本文
自主防災組織を作ろう
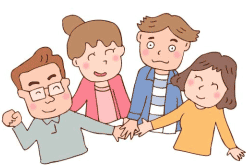 中越地震のような大地震から自分や家族の命を守るためには、さまざまな災害発生に備え、普段から十分な対策を講じておかなくてはなりません。
中越地震のような大地震から自分や家族の命を守るためには、さまざまな災害発生に備え、普段から十分な対策を講じておかなくてはなりません。
しかし、ひとたび大地震が発生すると、災害の拡大を防ぐためには、個人や家族の力だけでは限界があり、危険や困難を伴う場合があります。このような時、毎日顔を合わせている隣近所の人達が集まって、互いに協力し合いながら、防災活動に組織的に取り組むことが必要です。
災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組むための組織、これが「自主防災組織」です。
町内単位の自主防災会を作りましょう!

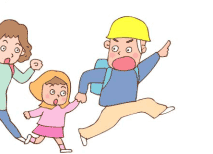
だれがなにを受け持つか?
自主防災組織が災害時に効果的に活動するためには、どんな活動をし、だれが何を受け持つかを決めておき、更にお互いの関係を体系づけておくことが重要です。
一般的な編成は、次のような形となるでしょう。
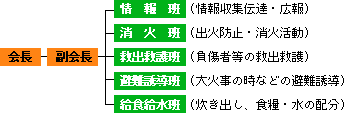
このほか、地域の実情に応じて、水害に対しての水防班、がけ地などに対しての巡視班などを設けるのも良いでしょう。
大災害が起こったときの自主防災組織の活動
(1)初期消火
地震による火災は、関東大震災のように市街地では、地震そのものによる被害を何十倍にも大きくします。火災が起こらなければ火に追われて避難する必要もありません。地震のとき、火を出さない、火が出たらすぐ消すことが何より重要になります。
(2)救出救護
大地震が起こると、建物が壊れたり、落下物などにより、多数の負傷者が出ます。しかし、救助工作車や救急車は、道路が通れなくなったり、渋滞で、動きがとれません。病院なども負傷者が殺到して処理しきれません。
このようなとき、自主防災組織の救助救護活動が非常に重要になります。
(3)情報連絡
災害が発生するおそれがある場合や発生した場合に、的確な対策をとるため、また、混乱防止のため、正しい情報の伝達や収集が不可欠です。
特に大地震が起こったときは、人間の精神が不安定ですから、デマが飛びやすく、パニックが発生しかねません。いち早く地域の被害状況や異常な情報を収集し自主防災組織の本部へ連絡します。本部はその情報を活用し、各班へ活動を指示します。
(4)避難誘導
避難の指示や勧告は、市町村長や警察官から出されますが、伝達困難な場合など、自主防災組織の自主的な判断で避難することも必要になります。
避難するとき、避難誘導班は、地域全員の安全を図るため、避難場所、避難道路の状況を調べ安全な経路を選定し、子ども、病人、お年寄り、体の不自由な人など自力避難が困難な人の搬送を行います。
(5)給食給水
地震で一番困るのは、水です。組織的な水の確保のため、備蓄した水の管理、井戸の確保に努めます。また、市町村の給水車が来るようになったら、整然と配分します。
流通の機能の麻痺で食糧の不足も考えられます。水と同様備蓄した食糧を管理し、大型の鍋、釜などを持ち出し、炊き出しを行います。
平常時の自主防災組織の活動
(1)普段から防災のポイントを確認しましょう。
初期消火のため
- 防火水槽、消火栓の位置の確認、消防ポンプ、街頭消火器の位置の確認
救出救護のため
- ジャッキなどはどこにあるか。負傷者を運ぶ医療機関はどこにあるか。医薬品の確保はどうすればよいか。
避難誘導のため
- 最寄りの避難地はどこか。避難路としてどこが安全か。
(2)防災資機材の整備
手入れが簡単で、誰でも使いこなせるものを用意しましょう。
(3)防災訓練
何度も何度も訓練をすることにより、初期消火、応急手当の方法について習熟しておきましょう。特に大地震のときは、普段頭で考えていることは、まずできません。頭よりも体の方が先に動くくらい訓練をし、なれておくことが一番大切です。
自主防災組織を結成するには
- 主に各町内会、もしくは組単位の結成をおすすめします。
自主防災組織補助金制度
- 会結成後、防災資機材の購入する場合、50,000円を限度として、購入費の2分の1を助成しています。
主に、ヘルメット、避難用具、消火器、消火栓ホース格納箱などの購入が多いようです。
補助対象資機材
| 区分 | 資機材 |
|---|---|
| 救助用資機材 | ヘルメット、投光器、コードリール、携帯用無線機、ハンドマイク、担架、はしご、救助用ロープ、チェンソー、エンジンカッター、バール、つるはし、掛矢、ジャッキ、鉄線カッター、一輪車、リヤカー、救命胴衣、トランジスタラジオ、その他救助活動に必要な資機材 |
| 救護用資機材 | 救急医療セット、防水シート、毛布、簡易トイレ、炊飯器具、給水用ポリタンク、避難所用具、その他救護活動に必要な資機材 |
| 初期消火用資機材 | 消火器、ホース収納箱、消火栓用ホース、管そう、組立用水槽、防火ヘルメット、バケツ、その他初期消火活動に必要な資機材 |
| 訓練用資機材 | 標旗、テント、ヘルメット、腕章、その他訓練に必要な資機材 |
| その他 | 保存用食料・飲料水、資機材収納庫、その他市長が必要と認めたもの |
自主防災組織ではこのようなものを購入しています。

自主防災組織結成の流れ(例)
 町内で防災出前講座などを活用し、防災意識を上げる
町内で防災出前講座などを活用し、防災意識を上げる- 町内役員で規約、組織、役割分担、一時避難所を検討
- 総会で結成を承認、防災予算などを予算化
- 市へ結成届け、規約、組織表等届出
- 補助金を活用し、防災資機材を購入(補助金申請)
- 定期的に防災訓練に参加、防災資機材の充実、広報活動を行う。
様式ダウンロード
自主防災啓発用パンフレット・申請様式
町内向けにご利用下さい。
結成のための手引き
- 自主防災組織結成の手引き [PDFファイル/1.2MB]
- 自主防災組織補助金要綱 [PDFファイル/135KB]
- ※組織編成図例[Wordファイル/29KB]
- ※任務分担表例[Wordファイル/32KB]
各種申請様式(結成届・補助金申請)
- 組織結成届け(記入例付き)
- 規約、組織表ひな型
- 市補助金交付要綱
- 市補助金交付申請書(記入例付き)

