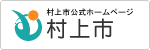本文
塩野町地域のお宝箇所情報
塩野町地域のお宝マップの作成
マップ作成の根本目的
地域内には新保岳などを中心に地域内外から多くの観光客が訪れています。
このほかにも地域内には、人々に大切にされてきた様々なお宝箇所があり、四季を通じ表情を変えて、それらは都会の人から見れば、どことなく懐かしさと親しみをあたえてくれるものでもあります。
これらの地域資源を凝縮して、集落の見どころ・地域観光マップとしてまとめ、地域全体で地域資源を共有するとともに、コミュニティビジネスの一助を目指して、作成しました。
【企画書】はこちらをご覧ください。[PDFファイル/89KB]
マップはこのたび、『しおのまち図』として平成29年6月30日に発行されました。(200円で販売中です。)
★お知らせ★地域のお宝マップ『しおのまち図』を発行しました!
マップ作成の方向性
全集落を散策し、地域の人の話を聞きながら、収集した情報を散策のつど、マップに落としてきました。
観光箇所として案内できる場所はないか、意外と知られていない重要な歴史の片鱗が残っているところはないか…といった視点で、神社・仏閣・石碑・ほこら・山・樹木・蔵・川・滝・清水(湧き水)・城跡・見どころ箇所・宿泊施設などの情報を収集しました。散策の模様を紹介します。
各集落の紹介



池の平(蒲萄) みよし様(早稲田) 姫宮神社(原小須戸)
※集落紹介文は各集落区長さんにご協力いただきました。(平成28年度現在)
| 集落名 | 集落紹介 |
|---|---|
塩野町 塩も人も行き交った街道沿いの旧宿場町。 | 塩野町は新保岳の麓に広がる越後平野の北端のまちで、豊かな水源と良好な日当たりによる農地と山の恵みは今も昔も私たちの自慢です。塩野町には出羽街道の宿場町の名残を残す町並みがあり、交通・交易・交流の要所として人の往来が盛んな場所だったことが伺えます。現在私たちは定住人口の安定と交流人口の増大を目指し、取り組みを続けています。盆踊り、子ども神輿、新保岳登山をはじめ、年末の大里様は毎年見物客が訪れます。誰でもいつでも帰ることが出来る場所であり、多様な変化を受け入れてきた人柄はフレンドリーで少々お節介ですが、心に響くこと請け合いです。 (塩野町集落区長 小田保積) |
松岡 今もなお、権現様に見守られる里。 | 当集落は20世帯(大滝姓19世帯・鈴木姓1世帯)が暮らす小さな集落です。また、自然・四季の富に包まれておりますが、少子高齢化が進む集落とも云えます。環境美化などの活動や野菜作りをしている高齢者の笑顔は活き活きとしており、パワーをいただいております。青年会が実施しているお盆行事の「ニジマスのつかみ取り」は集落民はもとより、帰省客が楽しみにしている行事であり、そこに集う老若男女の笑顔は何とも云えない喜びがあります。このように各世代が力を出し合って生活している集落で、また、集落の鎮守様「皇大神宮」にやさしく見守られている集落でもあります。 (松岡集落区長 大滝重秋) |
早稲田 塩の道の痕跡の残る太平山があります。 | 名所、旧跡は色々ですが、江戸時代に早川から塩野町まで、塩を運んだと言われる「塩の道」が早稲田、板屋越、早川の峰境にあります。その峰境の頂上(標高592メートル)に高さ1メートル、重さ200キログラムもある石塔、みよし様(大平山三吉神社)が鎮座しています。慶応4年5月(明治元年)に集落の力自慢の人が背負って運んだと伝えられ、家庭円満、身体堅固、商売繁盛のご利益があると言われ、集落では「みよしさん」「さんきちさん」の愛称で火の神様と伝わります。先人の願主の皆様が、集落の安全と繁栄を願い祀られたことを思うと、毎年「塩の道」整備とみよし様参拝を行い、後世に残すことが我々の使命と思っています。 (早稲田集落区長 富樫敏栄) |
原小須戸 「初なりきゅうりは天王様に」との言い伝えが残ります。 | 人口の減少、空き家が増えている現状でありますが、公民館が中心になって諸事業を行っています。1月は五穀豊穣・家内安全と集落安泰を祈念してのさいの神。3月はおばあちゃん方が主体となってのお釈迦様の百万遍念仏。ふれあいセンターがなかった24年前までは、個々の家を回り順番でやっておりました。そしてセンターでの花見。親睦を兼ねての食事会や余興などで半日ゆっくり過ごします。お盆には帰省客も参加できるよう個人の池をお借りしてのニジマス釣り。そして秋の収穫も終わってゆっくり出来る時期に、遊び感覚で出来る無理のない頭と体の体操などを集まって行っております。 (原小須戸集落区長 秋山久兵衛) |
本小須戸 夏は夜空に大輪の花。集落の心意気。 | 毎年恒例の仮装盆踊大会、マジックショーと、6回目となる大花火大会が昨年8月14日に開催されました。集落外の参加者や帰省者も年々多くなり、小須戸の夜空に大輪の花が咲くたびに大きな拍手や歓声が上がっていました。また、帰郷した人たちから「小さな集落なのに凄いよな」「私の故郷は小さい集落だけどこんな凄いことをやっているんだよと自慢しているんだ」などの声が聞こえてきました。30数戸の小さい集落ではありますが、年々盛大になり、小須戸にとって一年で一番熱く輝く日です。これからも集落内外の皆様のご支援とご協力をいただきながら継続していきます。 (本小須戸集落区長 山賀勝彦) |
荒沢 天狗松や山城跡を望む…権現さまのおわす蔵王山 | 荒沢の人口も80人と少なくなり、一人暮らしの家も出てきた。老人クラブ会員も半数となったがみんなで集まることに力を入れている。一番の自慢は「旅行友の会」で、会費を貯めて、今まで沖縄・北海道・岩手、また、荒沢の神社が白山神社なので、石川県の白山参りに行ってきた。名所は、蔵王権現様。毎年4月と5月にお参りし、昔は女性は参拝できないとされていたが、最近は一緒にお参りしている。伊利山の棚田の景色も見ていただきたい一つである。縄文時代の遺跡として荒沢石坂遺跡と沼遺跡がある。八巻山には山城跡もあり、福荘城といったそうだ。登り口にはネゴヤという地名があり、家来のいたところと伝わっている。 (荒沢集落区長 板垣清一) |
大須戸 かつての旅人が能の文化を伝えた里。今も旅人を迎えます。 | その昔大須戸二百竈と言われ、地区一番の大集落です。年中行事は公民館を中心に小正月行事(団子の木、さいの神)に始まり、神事能の奉納、お盆行事(盆踊り、相撲大会)を経て、注連縄奉納まで続いています。その他、サクランボまつり、薪能、能面展示などを催します。これらに各種団体の活躍が欠かせません。公民館・壮年会・大青会・若葉会・公民館婦人部・能保存会・農家組合・消防団・PTA・らんランクラブ・老人会(翁会)第一第二、ゲートボールクラブなどなど、多くの団体が活動するにぎやかな集落で、集落のセンターは毎日のように使用されています。農家民宿ひどこも地域おこし協力隊員の力も借りて繁盛しています。 (大須戸集落区長 中山金重) |
蒲萄 明日の道は名におうぶどう峠、…明神の住み給う所なりという…。 『東遊記』橘南谿(寛政7年)より | 春は、ふきのとうの芽生えで始まり、雪が溶けて薄緑の葉っぱがもくもくと覆い豊かな山菜の季節となります。夏は、稲の緑がどんどん伸びてきます。農作業の合間に棚田の奥にあるどんぐり清水で安らぎます。老人会で整備してくれた木陰のイスと花が疲れをいやしてくれます。秋は、運動会と実りの秋。稲刈り時期の前に集落の人々が集まり、競い、そして楽しいバーベキューの時間を過ごします。冬は、ぶどうスキー場。ロッジでは春に取れた山菜、秋のお米、赤カブを用意して集落のお母さんたちが笑顔で出迎えてくれます。蒲萄は里山の豊かな自然と笑顔があふれる集落です。 (蒲萄集落区長 岡田 比登志) |



矢葺明神(蒲萄) 皇大神宮(松岡) 蔵王山からの眺め(荒沢)
知ってだがね? ~塩野町のあれこれ豆知識~ ※『しおのまち図』より
地域の豆知識を少しご紹介します。このほかにも、お宝箇所がたくさんあります。詳しくは『しおのまち図』をぜひご覧ください。 
新潟県指定無形民俗文化財
「大須戸能」(大須戸)

村上市指定無形民俗文化財
「塩野町オサトサマ」(塩野町)
| 集落 | 塩野町地域のいわれ・歴史・名所あれこれ |
|---|---|
塩野町 「街道沿いの宿場町 」 | 塩野町は出羽街道の宿場町として栄え、江戸時代には、あの吉田松陰や松尾芭蕉も訪れました。米沢藩では塩野町を預り地とし代官所を置き塩を運んだといわれ、塩野町の地名は、海から塩を運ぶ上で重要な土地だったことに由来するといわれています。 |
松岡 「集落のいわれ」 | 松岡は、昔、猿沢と桧原の間の辺りに住んでいた人々が、「蛇身鳥」という鳥の化け物から逃れて現在の地に移住して開いた集落と伝わります。さらに荒沢へ移住した人々もおり、そのため、荒沢の蔵王権現は、お堂の入り口を荒沢のほうに向けても、かつての故郷の松岡に向いてしまうと言われています。 |
早稲田 「塩の道」 | 江戸時代、早川で作られた塩は、牛馬の背に乗せ、吉浦から山を越えて、早稲田へ下り塩野町まで運んだといわれます。さらに柳生戸を経て、山形県の小国方面(米沢藩)へ運んだようです。例年早稲田では、塩の道の整備を行っています。 |
早稲田 「 山城跡」 | 向山の一角に、中世戦国時代の山城跡があり、関口との境界の尾根道を小須戸川側に進むと、途中に「堀切」や大きな石を積んだ跡があり、帯曲輪の跡も認められます。これは「永禄年中北越村上城軍認書」という記録に「稲村の城番」(「稲村」は早稲田の古い呼称か)という記述があり、これがその山城と考えられています。 |
早稲田 「鉱山跡」 | 昭和20年前後~昭和35年頃にかけて、レアメタルの一種であるモリブデン・タングステンが採掘され、銅や硫酸化鉄も産出しました。今は、掘削坑や選鉱場の跡から当時を偲ぶことが出来ます。 |
小須戸 「姫宮神社ときゅうり」 | 昔、岩沢集落の住民は小須戸・布部・下中島の天王様に、初なりのきゅうりを持ってお参りしたとのことです。(斎藤・菅原姓の人は小須戸、飯沼・本間・大場姓の人は布部に、高橋姓の人は下中島にお参りした。)今でも、きゅうりの初物を神社に供えたり、きゅうりの作付けをしない家があるとのことです。 |
荒沢 「分校跡地」 | 荒沢にはかつて、昭和58年に閉校した塩野町小学校荒沢冬季分校がありました。明治40年に荒沢冬季派出所として開設以来、375名が学びました。 |
荒沢 「蔵王権現の言い伝え」 | 「女が参ったり、魚をお供えしたりして荒らすと、大蛇が出て雨(血の雨とも)を降らす」との言い伝えがあり、昔は、わざと女性がお参りしたりして雨乞いを行ったそうです。「蛙」の神様と無事「帰る」をかけて、戦時中には『戦勝祈』絵馬が奉納されました。 |
大須戸 「大行焼き」 | 明治5(1872)年ころ、東泉寺の住職と医師の中山恭庵らが中心となり、多治見から職人を呼んで茶碗などを作らせたのが始まりと伝わります。窯は、国道7号線から大行に入るすぐ左手の山際の斜面を利用した登り窯であったといわれますが、明治のなかばで廃窯となりました。 |
大須戸 「相撲の免状」 | 個人蔵。かつて中の里又吉(又作)という人が、両国日本相撲協会より、行司として、十両からの相撲を取り仕切ることの出来る免状をもらい、今も大切に保管されています。 |
大須戸 「さくらんぼ農園」 | 果樹組合で平成7年から作付けを開始し、現在は柿やさくらんぼを栽培しています。最近は、ぶどうの栽培も始めました。6月の第3日曜日には、「さくらんぼ祭り」がにぎやかに開催され、さくらんぼ狩りやバーベキューが楽しめます。 |
蒲萄 「矢葺明神の言い伝え」 | お産の神様として知られており、昔は境内に生える栃の木の実を妊産婦のお守りにしたそうです。「漆山神社」の名のとおり、漆業者にも信仰されています。また、源義家が矢で社殿の屋根を葺いたという伝説が残されています。 |
蒲萄 「どんぐり清水からの眺め」 | 標高約450メートルの高さに位置するため、春夏秋冬を通じ異なった風景を堪能できます。付近にある「大池」は、稲作生育に欠かせない貴重な水源となっており一年を通して枯れることはありません。 スキー場の上からも、この棚田を望むことができます。 |
蒲萄 「蒲萄鉱山」 | かつて蒲萄では「カナヤマ」と呼ばれた鉱山が栄え、元和年間(1615-24)に開発されたと言われ、当時は鉛が主でした。一時衰退しかけるも、明治時代に再採掘され、良質の鉱石を産出しました。昭和35年に閉山しましたが、今も山の斜面に、選鉱場などの鉱山の痕跡をかろうじて見ることが出来ます。 |