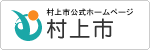本文
家庭でできる防災対策
1.家族で防災の話し合い
家族で防災の話し合い
- 日常の被害予防対策上の役割と災害時の役割の両方について決めましょう。
- 災害時の避難に支障のあるお年寄り、病人、小さな子どもがいる場合は、だれが保護を担当するかなども話し合いましょう。

いざというときの連絡方法
- 学校や仕事など家族が離れているときの連絡方法や避難場所を確認しておきましょう。
- NTTの災害伝言ダイヤル(171)も忘れずに。
避難場所の確認
- 避難場所や順路の危険箇所がないかなど散歩がてらに下見をしておきましょう。
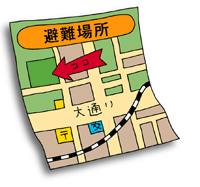
避難するときの8つの知恵
その1 「もう一度火の元を点検し、電気のブレーカーを切りましょう!」
- 倒れた家財の中に器具スイッチが入った状態の電気製品があったりすると、通電再開後、思わぬ火事の種になることがあります。
- 熱帯魚のヒーター、電気ストーブなどから火が出た例もあります。家のブレーカーを切って避難しましょう。
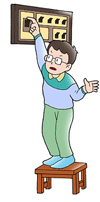
その2 「避難情報や安否情報を書いたメモを残しましょう!」
- 避難先や連絡先を書いた紙をドアや壁に貼るか書いておきましょう。
- 171災害伝言ダイヤルを使いましょう。
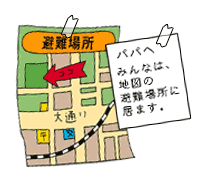
その3 「安全な服装で、頭や手足を保護しましょう!」
- 季節に関係なく長袖、長ズボン、手袋、ヘルメットなどを着用して、とがった破片や落下物などから身を守る。

その4 「荷物は背負って、必要最小限に!」
- リュックなどに詰め、手の動きを自由にして、避難行動を容易にする。

その5 「車は使わずエンジンを切ってキーを付けたまま徒歩で避難しましょう!」
- 道路は、救急車、消防車、警察パトカー、救援物資搬送車など緊急通行車両に譲る。
- 運転中に避難するときは、エンジンを切ってキーを付けたままにする。
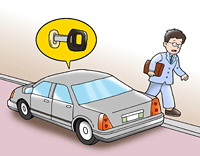
その6 「お年寄りや子ども、障がいのある方は背負うかしっかりとひもで結びましょう!」
- 手と手をつなぐのはかえってお互いの行動の自由を奪って危険を増す。

その7 「塀ぎわや狭い道、川そばの道などをできるだけ避けましょう!」
- 塀が倒れてきたり、路肩、護岸肩が崩れることがあります。
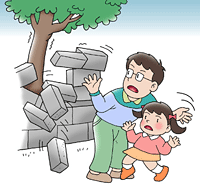
その8 「指定された避難所に避難しましょう!」
- 家族の連絡や安否の確認が容易になるとともに、応急物資、救急医療など避難生活の迅速な支援につながる。
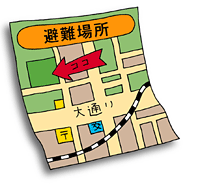
家具の安全な配置と転倒防止
- 家具の配置換えによって家の中に安全なスペースをつくれないか工夫する。
- 家具の転倒や落下を防ぐ方法を考え、そのための工夫などがあれば教え合う。
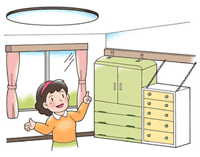
非常持出し品のチェック
- 家族構成を考えながら必要な品がそろっているかをチェックする。
- 定期的に新しいものと取り替える必要があるもの(食料、水、乾電池など)は、だれが担当するかなども話し合う。
- 建物倒壊に備えて分散配置をする。

2.非常持ち出し品のチェック
非常持出し品も一人ひとりで持てば、重さは軽くできます。建物の外や万一家が倒れても外から取り出しやすい場所に用意しておけば、用意した非常持出し品を一度に持ち出せなくても、あとから取り出すこともできます。
一次持ち出し品
避難したときすぐに必要になるもの。食料や水は少なくとも 2日分は用意しましょう。しかし、あまり欲ばりすぎると重量オーバーになり、避難にも支障がでるので注意を。重さの目安は男性で 15kg 、女性で 10kg 程度。同じ種類の品なら、できるだけ軽量でコンパクトなものを選ぶ。実際に持ってみることが大事。重すぎる場合は、その一部を家庭に保管しておくとよいでしょう。
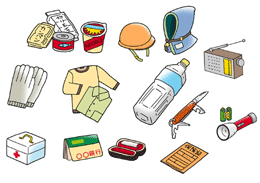
二次持ち出し品
救援物資が届くまでの数日間を自活するためのもの。できれば5日分程度は用意してください。1回で運べる量は限られますが、その後も何度かに分けて運ぶチャンスもありますので、水や食料などは少し多めにストックしておくとよいでしょう。

災害時に配慮を要する人々の非常持出品
病気、妊娠中の方、高齢や障害のある方などはそれぞれの状態に応じたものを備えておくことが大切です。
地震発生から数日間は、個別のニーズに対応するきめ細かい生活支援は困難になるおそれがあります。服用する医薬品や病状のメモ、生活行動を介助する補装具、衛生用品、消化しやすい非常食などを用意しておきましょう。
3.安全な住まいづくり
家具の安全な配置と転倒防止
寝室、子どもやお年寄りのいる部屋には家具を置かない
- 就寝中に地震に襲われると危険が大きい。
- 子どもやお年寄り、病人などは逃げ遅れる可能性があります。

家の中に安全なスペースを作る
- 家具は人の出入りが少ない部屋にできるだけまとめて置きましょう。
- あまり使わない家具は、処分することも考えましょう。
家具の安全な配置と転倒防止
- 畳の上に置くより板の間に置くほうが倒れにくくなります。
- 畳の上に置く場合は、家具の下に板を敷くなど工夫をしましょう。
- すべりやすい家具の脚には、すべり止めの器具をつけましょう。
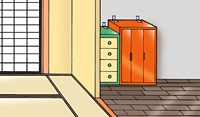
家具は壁や柱にぴったりつけておく、家具の重心を後ろ側に傾けておく
- 家具と壁や柱の間に遊びの部分があると倒れやすくなります。
- 家具の下に小さな板などを差し込んで、バランスをとりながら壁や柱に寄りかかるように固定しましょう。
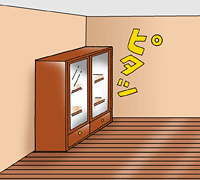
玄関や廊下などには家具を置かない
- 出入り口や通路に家具を置くと、転倒などでイザというとき通れなくなります。
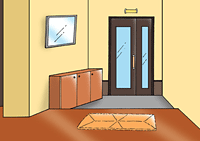
わが家の危険診断
- 家の内外をチェックして危険箇所を確認し合う。
- 危険箇所については、修理や補強の方法についても話し合う。
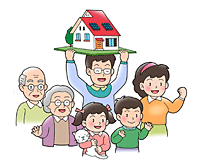
4.非常持ち出し品セット
いざという時は、ただちに避難しなければならないこともあります。そんな時に備えて、あなたの家にも一度に必要なものを持ち出すことのできる非常持出袋を常備しておきましょう。
災害が発生したとき最初に持ち出す一次持ち出し品
携帯ラジオ、懐中電灯、ろうそく、ヘルメット(防災ずきん)、非常用食料品(家族が2日すごせる程度)、水、衣類、生活用品(ライター、軍手、紙コップ、缶きり、ビニールシート、栓抜き、ウェットティッシュなど)、救急薬品、常備薬、預金通帳、健康保険証、印鑑、現金、その他御家庭で必要と思われるもの。
非常持出品
ポイント
手がふさがらないためにもリュックが原則!
- 食糧などは2-3日家族が過ごせる程度。欲張らないこと!
- 冬などは寒さ対策も忘れずに!
- 置く場所は玄関などすぐに取り出せる場所におく!
下記のセットの金額は大体の目安です。ホームセンターなどで揃えて下さい。
市で斡旋は行っておりません。ただし、おうちにあるものを寄せ集めでも何も問題ありません。
Aセット 5,000円位で売っています。

- 持出袋(オレンジ・イエロー)
- 携帯ラジオ付きライト
- スタンディングバッグ
- 軍手
- 五徳ナイフ
- 包帯、ガーゼ、三角巾
- 貴重品袋
- 乾パン(缶入り)
- 飲料水(缶入り)
- 食器セット
Bセット 3,000円位で売っています。

- 持出袋(シルバー)
- 携帯ラジオ付きライト
- 軍手
- 包帯、ガーゼ、三角巾
- 乾パン(缶入り)
- 飲料水(缶入り)
- 食器セット